論理とは何か、命題、集合と推論規則について
【目次】
1.論理とは何か
1-1.論理の始まり
1-2.対象の必要性
1-3.関係の必要性
1-4.分解の必要性
1-5.列挙の必要性
1-6.論理の定義
1-7.具体例、国語の論説文の書き方
1-8.論理についてまとめ
2.命題、集合とは何か
2-1.命題による対象化
2-2.命題の役割
2-3.命題の使い方
2-4.集合による対象化
2-5.集合の注意点
2-6.集合の効果
2-7.命題と集合の関係
2-8.高校数学で論理を学ぶポイント
2-9.集合についてまとめ
3.推論規則について
3-1.正しさの確認方法
3-2.推論関係と命題
3-3.分割と連鎖
3-4.推論と演繹
3-5.数学の論理の骨格
3-6.論理の練習(対偶と矛盾)
3-7.数学の理論構成
3-8.理論の正しさ
3-9.公理や原理の具体例
3-10.理論構成や正しさのまとめ
4.論理をより深く学びたい方へ
4-1.論理のあり様
4-2.数理論理学との違い
4-3.異なる構成の理由
4-4.高校数学マスターの価値
4-5.真理探究の枠組み
4-6.真理探究における価値
4-7.論理をより深く学ぶために
このページの内容をより深く理解するには、先に合理的に物事を考える方法を一読して頂くことをお勧めします。
論理とは何か
高校数学には、数学Ⅰ「集合と命題」という単元が最も初めに出てきます。なぜ、それが初めに出てくるのかというと、数学を正しく考えたり語ったりするための基礎が論理にあり、集合と命題がその論理の道具となっているからです。ただ、問題なのは、論理の道具についての説明はしているのに高校数学の教科書ではその前提となる論理とは何か、ということの説明をしていないことです。残念ながら、それでは集合や命題をきちんと理解することもできないばかりか、数学を論理的に考えることもできない、と言わざるを得ない現状があります。そこで、ここでは集合や命題について説明をする前に、論理とは何かの説明から始めていきたいと思います。
論理の始まり
初めて論理を論理学という形でまとめ上げたのは、ソクラテスの弟子のプラトンの弟子のアリストテレスでした。その目的は、ギリシャでそれまで積み重ねられてきた議論の方法を網羅し、特にソクラテス以降に精密化されたそれらの方法からその特徴や規約、法則性を汲み取ることでした。簡潔に言えば、正しく物事を考えるためにはどのように考えればよいのか、そこに法則はあるのかということでした。それもただ正しいだけではなく、いつでも誰にでも正しいと納得されるだけの正しさを求めました。つまり、それは合理的な正しさであり、合理的に物事を考える方法を突き詰めていった結果が、論理学という形になったとも言えるかと思います。
したがって、論理とは、その目的は合理的に考え述べること、にあります。逆に、間違えを含んでいたり、非合理な考えを許容することは論理に反するということになります。このような観点から論理というものを少し考察してみましょう。
対象の必要性
それでは、まず、何かをぼんやりと曖昧に考えている場合に、それは論理的な考えと言えるでしょうか。明らかに、何かをぼんやりと曖昧に考えていれば、間違えを犯しやすく正しくない考えに陥りやすくなるわけで、そうすると、論理とは、逆に、何か物事をはっきりと明確に考えること、であると分かります。
ここで、「何か」「物事を」という言葉を少し難しく言い換えると、考える「対象」というより的確な言葉があります。このこと自体が一例となっているように、一般に考える「対象」に対して、的確な名前を探して来たり、仮の名前を付けたり、時には新らしい名前を付けたりすること、つまり、何かしらの名付けをすることが、考えを明確化することの第一歩になります。
ちなみに、数学でXやYの記号を代数として数の代わりに用いるのは、仮の名前を付けることの代表例と言えます。このようなことを考えている「何か」の対象化、明確化と呼びます。
関係の必要性
さらに、論理のその必要な要素について考えを深めていきましょう。前段から論理的に考えるには、考えている「何か」を対象化して明確化することが第一歩であると分かりました。
それでは次に、もしも考えている「何か」の対象化ができても、それらがまったく無関係なことであったり、バラバラな対象であったりしたらどうでしょうか。誰かにそんなバラバラな対象を思いつくままに述べられたら、あなたであればどう感じるでしょうか。おそらく支離滅裂、意味不明と戸惑うのではないでしょうか。ここから分かることは、論理的に考え述べるためには、考えている対象が互いに関係を持ち、さらにその関係が明確化されていなければならないということです。
例えば、警察が事件を考える際には、事件に関係する人物を特定し、その人物間の関係を明確化します。さらに、事件の出来事と時間、場所の関係も明確化し、時系列で誰がどのような行動をどこでしたのかと考えていくことになります。そして、何よりそれらの出来事と関係する証拠を集め、どのように出来事と関係しているのかを明確にして矛盾がないよう合理的な説明ができるかを考えるわけです。その際に、無関係な出来事や証拠は捨てられ、関係する出来事と証拠の、その関係がどのような関係であるのかを明確にすることが重要になるわけです。それが引いては、事件、各人物、時間、場所、出来事などの考える対象の明確化にもつながるわけです。
つまり、論理的に考えるには、考える対象を明確にし、さらに対象間の関係も明確にする必要があるということが分かります。
分解の必要性
そこで、考える対象とその対象間の関係を明確にするためのコツが一つあります。例えば、複雑な対象を考えているのに、さらに複雑な対象との関係を考えたり、正しいかどうか分からない対象を考えているのに、より正しいかどうか分からない対象との関係を考えても、考えが堂々巡りになるばかりで埒があきません。
複雑で分かりにくい対象を考えるには、関係するより単純で分かりやすい対象を考え、その対象間の関係によって、前者をはっきりと明確にしていくことが大切になります。言い換えると、複雑で分かりにくい対象は、より単純で分かりやすい小さな要素に分解すれば良いということになります。
さらに一歩進めれば、複雑な対象を、必要十分な程度に単純な対象とその対象間の関係に分解して置き換えてしまうのです。そして、その単純で分かりやすい小さな要素は、小さくなればなるほど繰り返し議論の根拠として現れてくることが常で、このような例えば、原理や法則と呼ばれる対象を発見することが考えることの基本的な目標となります。
このような手順を分析と呼んだりしますが、分析が十分に終わり、間違いなく正しいと思える重要な要素をあぶり出すことができれば、今度はその小さく単純で分かりやすい要素の方から順々に大きく複雑で分かりにくい対象へと考えや説明を進めて行けば良いことになります。そうすれば、間違いが少なく効率もよいわけです。
列挙の必要性
加えて、対象と関係を明確にすること、ということから自然に導き出されることですが、考えていることに実は重要であるにも関わらず取り上げられていない対象があっては、つまり、考えるべき対象が隠されていたり漏れていたりしては、正しい議論を行うことはできません。同時に、議論が一部分だけに集中して、それ以外の考えるべき対象が抜け落ちてしまっていても、正しい議論を行うことはできません。だからこそ、疑問を持って関係する事柄をきちんと考え尽くすことが大切なのですが、逆に言うと、論理的に物事を考えるには、前提をあぶりだし、すべてを列挙し、全体に目配りすることが必要であることが分かります。まとめると、論理性を追求するのであれば、前提を含めて全体に渡るすべての対象を考えたり述べたりする方が良い、となります。
論理の定義
以上の議論を整理すると、少なくとも論理とは、考える対象とその関係を明確にし、単純で分かりやすい対象から順番に、前提を含めて全体に渡るすべての対象を、考えたり述べたりすること、と言えそうです。
具体例、国語の論説文の書き方
そこで、ここでは例えば論理的な考えや文章を必要とされる、国語の論説文を書く場合について考えてみましょう。まず、定義によると、合理的に考えたり、その考えを述べることを目的として、国語の論説文を書くわけなので、つまり、いつでも誰が読んでも正しいと納得できる文章を書くことが国語の論説文の目標となることを押さえましょう。
そして、考える対象を明確化するわけですから、名付けとしてタイトル、テーマが何なのかを明確な言葉にする必要があります。その上で、タイトル、テーマと関係するできる限り前提を含めて全体に渡るすべての対象について、より単純で説得力のある要素を探しながら列挙することになります。
そして、その各対象の関係を明確化、つまり、言葉で表していきます。その際には、もちろん、関係を正確に詳しく記述することも大切ですが、こことここは対立しているとか、類似しているとか、包含関係があるとか、因果関係があるとか、簡潔な言葉で関係を整理することも全体像を明らかにするためには大切なことになります。
そして、この関係の整理における最大のポイントは、後述の推論規則についてで詳しく説明しますが、これが正しいならばこれも正しいという、つまり、推論関係に最も注意を払うことです。なぜならば、論説文の目的は読者の納得ですので、論拠から結論を出す推論の流れが最も重要になるからです。例えば、こちらがあちらの理由になって、根拠になって、前提になって、具体例になっている、などという関係が推論関係です。
試験では、なかなか短時間で対象の分解、分析というところまでは難しいと思いますが、疑問を持って何が重要な要素になっているのかを探究し、それを見つけることができるかどうかが論説文の出来に直結してくることは確かだと思います。
最後に、各対象をその関係を考慮に入れつつ、前提となる重要な要素から結論まで主に推論していく順番に並べ直し、各対象の関係を述べていけば論理的な国語の論説文が完成する、という手順になります。この手順が最も基本的な国語の論説文の書き方となるわけだと思いますが、後は、読む人のレベルに合わせて、読みやすく関心を引くように文章の展開を工夫したり、飾りを増やしたり、ということも文章には必要になってきます。
ただ、少し付け加えると、文章を書くというのは、たとえてみると複雑な生物の体の設計図が一列の遺伝子配列に書き込まれているのと似ていて、複雑な概念を紐解き、整理して、誤解が生じないように正確に効率的に一列の文章に書き込んでいく作業と言えるのだろうと思います。そのため、遺伝子が一見単純な配列で構成されているのに、実は沢山の複雑な機構を持っているのと同じく、良い文章を書くには様々な設計思想やテクニックがあることも学ぶ必要があります。その最も基本的で代表的な枠組みの一つが前段までの内容だと思ってください。
論理についてまとめ
ここまでで、論理の大枠については理解することができたのではないかと思います。この大枠は、数学の論理についてもまったく同じことが当てはまります。ただ、その対象が数学になったというだけです。しかし、数学に当てはめる論理は、さらにその合理性、つまり、いつでも誰にでも正しいと納得してもらえること、を高めるためにさらなる精密化が図られています。冒頭でも少し触れましたが、その精密化のための道具が、命題、集合、推論規則などです。次節からは、その精密化の道具をなぜそれが必要なのかという背景から見ていきたいと思います。
命題、集合とは何か
命題による対象化
冒頭で紹介したページでは、「考える」ということは、『正しい答えを出すために言葉を使って行われる行為』であると述べました。つまり、考えることは答えを出すために行っていて、答えには正しい、正しくない、分からないなどの評価があるという考察を行いました。数学においても、答えという考える対象が正しいのか、正しくないのかということが主な議論の中心的な内容になります。
そこで、前述の通り、論理的に物事を考える方法の第一として、対象を明確化することがあると挙げましたが、高い論理性を議論に求める数学でも、正しいのか、正しくないのかを評価する対象をより明確化しょうとします。その明確化のために、正しいのか、正しくないのかを評価する対象の文章を別名として、そしてその単位として、命題と呼んでいます。
命題の役割
例えば、長々と続く千文字以上の長文を対象として、この主張は正しいのか、正しくないのかと問われても、全体としては何とも答えに窮するものです。そのような場合、その長文を意味のある区切りで「命題」に分けて、各命題の正誤を判定すれば、より正確な議論を行うことができます。
さらに例えば、ある人が主張する意見が、聞くたびに変わるのに本人はいつも同じことを言っていると主張する場合も、割と良くある議論が不正確になってしまう典型的な事例です。こんな場面で、その意見を書き留めて命題として明確にしておけば、その命題の解釈は様々に変わる可能性はあっても、文字情報としては不変の値を保つことができ、命題として一意であることの保証にもなります。このように、何らかの主張を区切りを付けて一つの単位として命題と名付ければ、議論を正確に行うことができるようになるのです。
命題の使い方
例えば、数学の教科書を読んでいて、「定理」が出てくることがあります。これも正しいのか、正しくないのかを評価する対象となっている明確な区切りのある文章なので、「命題」であると言えます。その他にも少し難しい教科書を読めば、「補題」「系」「公理」などという言葉が出てくると思いますが、これらもすべて定義からすると「命題」であると言えます。
さらに言えば、それらの証明の中にも、正しいのか、正しくないのかを評価する対象としての文章のまとまりがあるはずで、それらもすべて「命題」であると言えるわけです。つまり、数学は命題を議論の基本的な単位としていると言えるのです。
さらに踏み込むと、基本的な単位である命題の正誤を積み上げながら議論を行うのが、数学の流儀、合理的に数学を考えるための方法であるとも言えます。その際に、それらの重要性や議論の中の位置づけとして、「定理」「補題」「系」「公理」などの名称が命題についているわけです。
ちなみに、考える対象が他の対象や関係を考える対象に含んでも良いように、命題も他の命題をその命題の中に含んでいても良いということに注意しましょう。例えば、「定理Aが正しいならば定理Bも正しい」という文章があったら、この文章全体は命題ですし、定理Aや定理Bも命題ということになります。つまり、命題は考える対象としての区切り、あるいは、たんなる単位であるということです。これは、集合の要素として集合を考えても良いということとも同じことです。
集合による対象化
命題についての説明は以上で終わりますが、命題との関係も深い集合についてページ冒頭でも触れましたので、論理との繋がりで、なぜ集合が数学では必要なのか、集合とは何か、ということを論理の道具としての集合という観点から説明をしたいと思います。
集合は19世紀にカントールによって発見されました。繰り返しですが、論理的に物事を考える方法の第一として、対象を明確化することがあると指摘しましたが、集合が発見されるまでは数学の対象は、それまでの論理学の通例通り、概念として対象化されており、他の学問とそれほど異なる対象の捉え方をしていませんでした。
その捉え方は、どちらかというと名前と定義によって定められた概念からその概念に含まれる対象が何かという、外側から内側を推論するという方向性を持っていたものと思います。しかし、その方法ではどうしても、ある概念にある対象が含まれているのかいないのかということが、言葉の意味の類推に頼らざるを得ず、曖昧になる傾向があります。
集合の画期的なところは、数学で考えられる対象の多くには、要素から集合が構成されているという共通の形式があることを発見し、要素を明確化することで考える対象、つまり、集合を明確にしょうとしたことにあります。つまり、内側から外側を明確化しょうとする、それまでと逆の方向性を提示することができたことにあるのだろうと思います。
集合の注意点
ただ、少し注意を要するのは、たしかにどんな対象であっても集合らしい形式を取ることはできるのですが、集合の形式となじむ対象となじまない対象というのはあると思います。例えば、鳥という対象を考えるときに、従来のように鳥という概念を考えるのは妥当です。つまり、「鳥は羽を持つ動物」と定義して、すべての動物を羽を持つかどうかで判別していくことはできて、しかし、やはり、そこには羽があるのかないのか分からない動物(例えばモモンガや始祖鳥)が混じり、それらを区別するために永遠と定義の延長を強いられ、「概念」という枠組みの曖昧さが露呈するわけです。
一方で、概念が曖昧であるからと言って、集合ならば鳥という対象を明確化できるかというと、「羽を持つ動物」を集めてきて、これを要素とする集合を「鳥」と名付けると試してみたところで、そこには羽があるのかないのか分からない動物は歴然として存在してしまうわけで、逆に、不正確な集合を構成することしかできないという結論になります。
このように考えると、集合は要素を明確にすることができる数や幾何やその他の数学的な対象と相性が良いことが分かり、集合を使って生じる矛盾やパラドックスの多くは、不明確な要素を無理やり集合という形に押し込んだ時に生じてくるようです。
集合の効果
このような問題が多少はあるにせよ、集合によって数学は考える対象を明確化するための枠組み、強力な道具を手に入れることができました。そのため、集合の発見以降、数学で考えられる様々な対象は集合の形が取られるようになり、数学は単に数学的な対象とその対象間の関係を考える学問から、まるで集合の要素とその要素間の関係を考える学問と言えるかのような変貌を遂げてきました。
命題と集合の関係
例えば、命題の中身も主たる数学的な対象は集合化されて、命題は集合の要素とその要素の関係を記述する部分から構成されるという数学に特殊化された命題の捉え方、形式を持つことになります。
もう少し詳しく説明すると、数学においては概ね、含まれる数学的な対象の取る値によってその真偽が変わる文や式、あるいは命題を条件と呼び、条件を命題の構成単位とします。そして、その条件の中の数学的な対象を上述のように集合化して、条件あるいは命題間に成り立つ推論関係を集合の包含関係と対応させて考えます。(より詳しくは、集合と命題についてや対偶の証明についてをご覧ください。)
このように現代の数学では、集合があまりに当たり前に活用されているために、高校数学でも学習する分野名は「集合と命題」と言って命題よりも集合が中心となっています。その内容も前述の通り、集合を含んだ形式の命題の解説が多くなっています。そのため、命題の理解や命題と集合の区別がしにくい側面があります。
高校数学で論理を学ぶポイント
しかしながら、ここまで説明してきたことから分かると思いますが、集合は数学的な対象に特殊化された側面があるので、命題よりも学問的にその応用範囲が狭いと感じられます。そのため、数学学習の一つの大きな目標である論理的な思考力の養成という観点からは、命題を用いることに習熟した方が数学以外にも応用が効くようになり、優れた教育内容になるだろうと思います。少なくとも命題と集合を混同したり、切り離すことのできない状態で数学教育を終えるのは残念なことです。
つまり、高校数学でも命題自体は解説していますので、命題の解説の充実と集合との切り離しをきちんとすれば良いだけの話なので、本サイトでは集合と命題についてページなどでも詳しく説明をしています。ただ、高校数学で学ぶ論理関連の内容はそのあたりの解説までで、それ以上に命題や集合、論理を形式的に扱う手法などの詳しい数理論理学の内容は大学での勉強となります。もちろん、学ぶ意欲のある方は、高校生であろうとどんどん学べば良いと思います。学ぼうとして分からないからこそ大学に行くのであって、そのくらいの意欲があった方が大学での学びは充実すると思います。
集合についてまとめ
最後に集合について、論理的に物事を考える方法という観点から一言でまとめておくと、論理的に考えるには数学に関わらず対象を明確にすることが大切ですが、数学の場合にはその一手段として、数学で考える主な対象を集合という形で明確化して考えていく、と言えるかと思います。
大学では、数に限らず空間から関数まで様々な数学的な対象を集合として捉え直していきます。さらには、様々な数学的な対象を分解して捉え直し、共通の特徴や性質を集合に加えていくことで、数学的な対象を再構成するという方法を取ります。
そのため、何でも集合が出発点となり、何を対象として考えているのかが分からなくなり混乱する人もいます。ただ、どんな学問でも何らかの対象を考えていることは同じであり、数学の場合は、数や幾何などの数学的な対象を考えており、集合はその対象を明確化するための道具に過ぎないという基本が分かっていることが大切です。
それが分かっていさえすれば、どんな数学的な対象を考えるときも、考える対象のひな型である集合が出発点となることは当たり前と合点が付き、集合ではなく集合に加えられる特徴や性質が何を対象として考えているのかという疑問に対する答えを持っていること、つまり、それらの特徴や性質が当てはまるより具体的な数学の対象をまとめて考えているのだ、ということも割とすぐに分かり、戸惑うことも少ないだろうと思います。
ちなみに、集合の要素の定義でも、集合が入った命題においても、数学は言葉の意味による定義という曖昧な手段を極力排してきた歴史を持つようで、数学的な対象の明確化は、できるだけ言葉の意味によるのではなく、数学的な対象間の関係によって狭めていく、明確にしていく、規定していく、という数学の流儀があるように思います。
前述の通り、論理的に物事を考える方法の第二として、対象間の関係を考えることを挙げましたが、数学の流儀は、それを徹底するところにあるかと思います。例えば、集合間に定義される関数や写像の概念はその一典型例と言えるだろうと思います。さらに次節では、数学が最も重要視する命題間の関係、推論規則について解説したいと思います。
推論規則について
正しさの確認方法
少し復習から始めると、合理的に物事を考える方法の「考えるとは何か」の節では、「考える」ということは、『正しい答えを出すために言葉を使って行われる行為』と定義することができました。では、考えて出した答えに対して、その答えが正しいのか否かをどのように判断すれば良いでしょうか?
まず、簡単に思い付くのは、できることならばその答えを具体的な事例に当てはめれば、もしも、間違っているのであれば間違いと言えるし、もしも、正しければ、少なくともその当てはめた具体例については正しいことが分かります。
ただ、この方法では、答えが合理的な答えであると主張している場合には、つまり、いつでも誰にとっても正しい答えであると主張している場合には、すべての場合に答えを当てはめることはできないので、その正しさを合理的に確認することはできない、ということになります。ちなみに、もちろん一つでも正しくない事例が見つかれば、合理的には正しくないことの確認はできます。
つまり、答えだけではその答えが合理的に正しいのかを判断することはできないということが分かります。ただ、答えが正しいのかどうかを判断するための対象としては、その答えか、その答えを導き出した考えか、しかありません。そこで、答えを導き出すために考えた、その考えが正しいのかどうかで、答えが正しいのかどうかを判断するしかないということが分かります。つまり、答えの根拠、理由、論拠などが正しいかどうかで、答えが合理的に正しいのかどうかを判断しようということになります。
推論関係と命題
この答えと答えを導き出した考え、つまり、答えの根拠、理由、論拠などとの関係を推論関係と言います。具体的に言うと、ある対象が正しければある対象が正しい、という二つの対象の関係を一般に推論関係と言います。たしかに、根拠が正しければ答えが正しい、理由が正しければ答えが正しい、論拠が正しければ答えが正しい、という関係が成立しています。
前節では、命題とは、正しいのか、正しくないのかを評価する対象ということを学びましたが、そうであるならば、ある命題が正しければ別の命題が正しい、という風に推論関係の対象に命題がぴったりと当てはまるので、推論関係は、命題が正しければ別の命題が正しいという、二つの命題間の関係であると言い換えられることが分かります。
ここで、答えも正しいか、正しくないかを判断する対象なので命題と言え、答えの正しさを判断するための答えを導き出した考えも、やはり、正しいか、正しくないかを判断する対象なので命題と言えます。つまり、答えの正しさを判断するために答えを導き出した考えが正しいかどうか判断する、ということは、ある命題の正しさを推論関係にある他の命題の正しさで判断するということに他ならないことが分かるのです。
分割と連鎖
さらに前節では、考えはたくさんの命題に分割することができるということも学びました。それはつまり、答えを導き出した考えも、たくさんの命題に分割できるということであり、答えを導き出した考えの正しいかどうかは、それらすべての分割された命題が正しいかどうかにかかっていることが分かります。
具体的には、答えと推論関係がある命題が少なくとも一つあって、その推論関係はその命題を仮定として答えを結論とする向きであり、くわえて正しい推論関係であり、さらにその根拠となる命題も正しくなければなりません。そのためには、さらに続けて、推論関係も命題なので、その推論関係が正しいことを同様に導かなければなりませんし、根拠となる命題が正しいことも同様に導かなければなりません。そして、その各命題は複数のさらに別の命題によって構成されている場合もあるわけです。
結局、答えを導き出した考えを分割して表れる、すべての命題が正しいかどうかとは、上記のように答えから推論関係を辿って表れるすべての推論関係を含んだ命題の正しさであることが分かります。つまり、ある答えの正しさというのは、疑問を持ってその推論関係をたどっていくと表れる、すべての推論関係を含んだ命題の正しさによって決まるということが分かります。
このように考えると、答えから推論関係を辿るうちに大量の命題が表れてきて、収拾がつかなくなるように思います。実際に、収拾がつかなくなることも多いでしょう。そのために、論理とは何かで前述した考察の方法を生かす必要があるわけです。分解の必要性でも述べましたが、その大量の命題の中から繰り返し根拠として用いられる確実な命題、つまり、いくつかの原理や法則を見つけ出すことが真理探究の目的となりますし、このことは後述の数学の理論構成の説明で改めて触れますが、実際に、ある程度はそれができているのが数学や科学ということになります。
推論と演繹
この答えから疑問を持って推論関係をたどること、の逆を行えば、正しいことから正しいことを導き出していき、答えにたどり着くことになります。つまり、正しいことをたどって行きさえすれば決して間違えることはない、というこの原理を演繹とか、演繹の連鎖と表現することがあります。
そう考えると、正しい答えを導き出すためには、この演繹の連鎖を生み出す推論関係が非常に大切であることが分かります。先ほどの国語の論説文の解説において、様々な関係の整理における最大のポイントは、推論関係の整理だということを指摘しましたが、正しい答え、正しい結論を導き出すための考えを文章にする国語の論説文において、演繹の連鎖、つまり、推論関係が最も大切であることは、このことから分かって頂けたのではないかと思います。
これは国語の論説文のみならず、数学を含めて論理において最も重要な関係は、あるいは、論理の骨格となる関係は推論関係であると、このような視点からは言えるのではないかと思います。数学においては、この命題を推論関係でつないでいくという考え方や論証方法が、論理の明確化のための数学の流儀になっています。
数学の論理の骨格
ここまで、数学の論理の骨格は、命題とその推論関係にあるということが分かりました。推論関係は、命題間の推論規則とも呼ばれ、記号の⇒で表したりします。加えて、ある命題から別の命題を作り出す規則として、(ある命題「ではない」)という命題を表すための否定¬や、(ある命題「かつ」ある命題)という命題を表すための積∧や、(ある命題「又は」ある命題)という命題を表すための和∨を用いたりします。数学の論理の骨格は、命題とこの4つの命題間の関係で基本的には構成されていると考えてよいと思います。
前節では、数学は命題の主な対象を明確化するために集合を用いることを解説しましたが、そのように命題の中に集合を持ち込んで考える場合には、集合の中の「すべての(任意の)」(記号∀)要素を考えるか、「ある」(記号∃)要素を考えるかも重要になります。したがって、集合を用いる数学の論理の骨格としては、以上の六つの言葉や関係を理解すれば、あとはそれらの組み合わせですべてが成り立っていると考えて良いと思います。
このように、数学における論理の枠組みは、最も重要な推論関係を軸にシンプルに洗練させてあると言えるのかと思います。簡単で分かりやすい、と感じた方も多いと思いますが、簡単で分かりやすい、ことが複雑なことを考えるための基礎としては非常に大切になってくるわけです。
論理の練習(対偶と矛盾)
例えば、論理の練習として、数学の論理関連で良く出てくる「対偶」や「矛盾」について少し説明をしておきたいと思います。対偶とは、命題「A⇒B」が正しければ命題「¬B⇒¬A」が正しいということを表した言葉ですが、通常、高校数学の教科書では集合を用いて説明を行っていますが、なかなか分かりにくい印象を持つ人も多いと思います。
けれど、そもそも集合が発見される前に対偶という言葉は成立していますし、もちろん、集合で扱えない対象に対しても対偶は成立します。そして、その証明も概略はわりと簡単ですので紹介しますと、命題A⇒Bが成り立つときに、もし対偶¬B⇒¬Aが成立しないとすると、命題¬B⇒Aが成り立ちます。したがって、命題¬B⇒A⇒Bが成り立ち、つまり、命題¬B⇒Bが成り立ちます。そのため、命題Bが正しくない場合には、命題Bは正しくもなく正しくもあるという矛盾が生じてしまいます。したがって、対偶は成立し、命題¬B⇒¬Aが成り立つしかないわけです。(より詳しくは、対偶の証明についてをご覧ください。)
ここで、通常、矛盾とはある命題と別の命題が両立して成立しないことを表しますが、この証明のように、結局のところ、矛盾の証明のためには、ある命題が正しくもあり正しくもないというところに帰着させることになります。例えば、ある命題A「甲は白い服を着ている」と別の命題B「甲は赤い服を着ている」は、明らかに矛盾していますが、それは、命題B「甲は赤い服を着ている」⇒¬A「甲は白い服を着ていない」からなのです。複雑な命題間の矛盾を詰めて考えるときには、こんなこともコツになるような気がします。
加えて、対偶を矛盾に適用すれば、とても面白いことが分かります。命題Aと命題A⇒Bが成り立つときに、命題B∧¬Bも成り立つという矛盾が導き出されたとすると、命題A⇒Bの対偶である命題¬B⇒¬Aも成り立つので、これと命題¬Bが成り立つことを併せると、結果として命題¬Aも正しいということになってしまいます。つまり、結論である命題Bが矛盾すると、命題Bを導き出した根拠となる命題Aも矛盾してしまうのです。
そうすると、命題Aを導き出した命題も、その前の命題も、という風に矛盾は推論関係を遡って、前提となるすべての命題が矛盾してしまうわけです。このように、たった一つの矛盾が理論全体に影響してしまう、そのため、理論には一つの矛盾もあってはいけない、と数学の場合は考えるのです。(より詳しくは、矛盾と背理法についてをご覧ください。)
数学の理論構成
「対偶」や「矛盾」を考えていると、だんだんと数学の論理の扱い方にも慣れてくるかと思いますが、最後に、推論関係によって成り立つ数学の理論全体の構成について、さらに少し触れて論理についての話を終わりにしたいと思います。
先ほど、ある答えの正しさは、疑問を持ってその推論関係をさかのぼって行って表れる、その答えと推論関係で結ばれるたくさんの命題の正しさによって決まると指摘しましたが、よく考えるとおかしな話で、そのように演繹の連鎖を逆にたどっていったときに、いつ、その連鎖は終わるのでしょうか。
もしも、終わりがあるとするならば、その終わりの命題には、根拠や理由がないということになり、逆に終わりがないとすれば、無限に演繹の連鎖が続くことになり、正しさの根源となるはずの命題は認識できないと宣言するようなものです。結論から言うと、ユークリッドの原論の時代から、数学や科学の理論というのは、前者の、終わりの命題には根拠や理由がないという形式を選択しています。
数学では、それを皆が受け入れざるを得ない真理という意味で公理と呼んだり、科学やその他の学問では、原理とか根本法則などと呼んでいます。つまり、数学や科学の理論は、その公理や原理から理論に含まれるすべての命題を推論によって演繹していくという構成を持っています。
理論の正しさ
このような数学や科学の理論構成を学ぶと冒頭で紹介した合理的に物事を考える方法を読んで頂いた方は、ソクラテスの問答法やデカルトの真理探究法が生き生きと現在の数学や科学の理論の中にも生きているということをお気付きになるのではないかと思います。くわえて、公理や原理には根拠や理由がないというのは、まさにソクラテスの言うところの無知の知を目の当たりにしていると感じる人も多いだろうと思います。
それでは、公理や原理には根拠や理由がないので、正しさの欠片もないのかというと、そうではないわけです。逆に、正しさの欠片もなければ、そのような公理や原理から出発する理論全体が無価値であり、あってもなくてもよい理論になるというわけです。
ここでは、本節の初めに戻って考え直しましょう。本節の初めの考察によると、命題の正しさの判断には二通りありました。一つは、命題をそのまま具体例に当てはめて正しさを判断する方法、もう一つは、命題が導き出された命題に遡って正しさを判断する方法、この二通りです。前者は、当てはまる具体例では正しいが、普遍的な合理性の保証にはならないとして、後者の方法に踏み込んだのですが、しかしながら、後者の方法も限界があるということがここで分かったわけです。
つまり、どちらにせよ正しさの判断は不完全で、普遍的な合理性の保証にはならないわけですが、よく考えると、前者の方法では、少なくとも当てはまる具体例については正しさを確認することができるのです。それも、当てはめた命題のみならず、当てはめた命題を演繹してきた公理や原理の正しさも、少なくとも当てはめられた具体例においては確認することができるわけです。
公理や原理から演繹される命題の数は多いので、理論の末端の命題よりも当てはめられる具体例も格段に多くなり、その正しさを確認できる具体例も増えていきます。正しさを確認できる具体例が増えるほど、より正しそうな命題であるという認識は高まり、無価値な公理や原理、その理論との差別化ができるということになります。
したがって、公理や原理の正しさを判断するには、演繹による具体例での確認が非常に大事になってくるということが分かります。逆に、公理や原理が当てはまらない具体例を見つけられた時に、あるいは、その間違えや矛盾を抱える命題を見つけられた時にこそ、より普遍的で価値のある、新たな公理や原理の発見の門口に立ったと言えるのです。
それに、そもそもある命題の根拠に他の命題を用いるときに、元の命題よりも正しくなさそうな命題を根拠として用いるということはありえず、少なくとも元の命題よりも正しそうな分かりやすい命題だからこそ、根拠となるわけで、それをさかのぼったところの公理や原理が最も正しそうで分かりやすい命題であるのは当然とも言えます。つまり、デカルトの真理探究法で主張されているように、物事を分解してより分かりやすく単純な要素を見つけること、とは突き詰めれば公理や原理を見つけること、真理探究の考察に他ならないわけです。
公理や原理の具体例
例えば、ユークリッドの原論に挙げられている一つの公理「同じものに等しいものは、互いに等しい(A=B∧A=C⇒B=C)」について考えてみましょう。直観的に正しいから公理として認める、で済ましてしまっては、これまでの議論が意味のないものになってしまいますので、その公理として「直観的に正しい」という感覚がどこから来るのかを疑問を持って考えてみましょう。
このように単純で分かりやすい命題は、当てはめられる具体例も非常に多く、それが「直観的に正しい」ことの基礎付けになっているのだと思います。当てはめられる具体例が、本当にいくらでもあるのですが、例えば、AさんとBさん、AさんとCさんの身長が等しければ、BさんとCさんの身長も等しい。AさんとBさん、AさんとCさんの帽子の形が等しければ、BさんとCさんの帽子の形も等しい、などです。
たしかに当てはめられる具体例が非常に多くありますので、公理としての正しさも確実のような気がします。けれど、よく考えてみてください。同じものとは一体何でしょうか、AさんとBさんは異なる人ですが、身長が同じもの、帽子の形が同じものと言っているわけで、AさんとBさんが同じものと言っているわけではないのです。
逆に、AさんとBさんから切り離した、身長や帽子の形というのは、一つの値、一つの形であって、そもそも同じものか異なるものかを比較することすらできないのではないでしょうか。つまり、同じものか異なるものかという判断の前提には、比較するという行為があって、さらに、比較するという行為には少なくとも二つの異なるものが必要なのではないでしょうか。
実際に、二つのすべてが同じものを見たことがある人はいますでしょうか。二つであれば何かが異なり、すべてが同じであれば一つであるので、二つであることとすべてが同じであることは矛盾してしまうのです。そう考えると、同じものとは、少なくとも二つの異なるものに共通する一つのものを指す言葉だということが分かります。したがって、この公理を少し修正すると「あるものと共通するものがある異なるものは、互いに同じ共通するものがある(\(x\in A\cap B\land x\in A \cap C \Rightarrow x \in B\cap C\))」と代えた方が良い気もするわけです。
例えば、どのように用いるかというと、集合Zの要素をAさんとBさんとCさんとして、さらに、AさんとBさんとCさんを各自の身長と帽子を要素とする集合Aと集合Bと集合Cと考えます。そうすると、集合Zの中で各集合が等しいという関係は、上記の定義によって\(x\)の全体集合に身長を取るのか、帽子を取るのかによって変わることになります。つまり、\(x\)の全体集合が集合Zの中の等しいという関係を決定する基準になるわけです。さらに、その\(x\)の全体集合の取り方によって集合Zに異なる等しいという関係を定義しうることも、ユークリッドの公理よりも明確になるのだろうと思います。
これより先は発展的な内容となるので、興味のある方は私のHPの等しさと同値関係についての一考察をお読みください。
他にも原理中の原理と言えば、デカルトの哲学の第一原理「われ思う、ゆえにわれ在り(われ思う⇒われ在り)」というのもあります。存在の成立が思考の成立の必要条件、思考の成立が存在の成立の十分条件になっているという命題と理解しています(必要条件と十分条件について詳しくは必要条件と十分条件についてをご覧ください。)。このような原理であっても、おそらく現代の視点からすると多様な修正がなされているだろうと思いますが、興味が湧く人は、頭の体操のために「少しだけ」考えてみてはいかがでしょうか。(存在と認識、絶対性と相対性が論点というところでしょうか。)
さらに、上記と少し似た構成なので、このページの内容を例に取れば、「1-2.対象の必要性」を簡潔な命題にすれば、命題\(P\)「考える⇒考える対象がある」となり、「1-3.関係の必要性」を命題にすれば、命題\(Q\)「考える対象がある⇒考える対象間の関係がある」となるかと思います。そして、命題\(P\)はなかなか堅牢な命題、つまり、公理に近いのではないかと私は感じています。少なくとも私には、対象を持たずに考えるということが、想像できないからです。
同時に、命題\(R\)「考える⇒真偽がある」を前提とした場合に、対象一つのみを考えるとしたら、対象という認識のみでは真偽も存在しないので、命題\(R\)に反することになり、考えるためには少なくとも対象は二つ必要になります。くわえて、対象が二つあっても両者に何の関係もなければ、やはり、真偽は存在しないので、命題\(R\)に反してしまうため、考える対象の二つ以上の対象間には何らかの関係があると言えます。したがって、命題\(Q\)を導くことができました。
例えば、二つの対象として対象\(A\)「真偽」と対象\(B\)「存在」があって、さらに、関係\(S\)「\(X\)が\(Y\)」があって、始めて命題\(T\)「\(S(A,B)\)」、つまり、「真偽がある」を考えることができるということだと思います。ちなみに、命題\(P\)の仮定「考える」という命題には、主語が省略されていると考えて良いと思います。ここで命題\(R\)は、議論を簡単にするために前提としましたが、命題\(R\)を前提としなくとも、対象を考えて理解するためには、対象の認識のみではやはり足りないだろうことも指摘しておきます。
より詳しく知りたい方は、私のHPの対象と関係についての説明などをお読みください。
理論構成や正しさのまとめ
最後に数学や科学の理論の構成や正しさについてまとめると、数学や科学の理論は、公理や原理とそこから演繹される命題から構成され、その正しさは当てはめられる具体例によって基礎づけられている、と言えます。ただし、公理や原理は、直観的には確かめられない場合もあるので、そこから演繹される命題を具体例に当てはめて、そこから正しさが裏付けられることもあり、逆に、そのように確認された公理や原理の不完全ながらも一定の普遍性のある正しさから演繹されることで、理論の中の各命題は直接、具体例に当てはてはめる前であっても一定の正しさの保証がなされることになります。
このように、一見理論の正しさは、公理や原理と、その理論の中の各命題とで相対的に担保されているように見えますが、実のところは、その正しさはすべて当てはめられる具体例によって基礎づけられているわけです。数学ではよくあることですが、これが例え理論の理論、理論の理論の理論、、として発見された理論であっても、同じ構成を持っています。極論すると、当てはめる対象のない公理を演繹しても理論は得られますが、そのまますべての命題について当てはめる対象がないのであれば、たとえその理論の中の演繹の正しさが確かめられても、理論としての正しさはまったく確かめられないということになります。
ここまで理解することができれば、高校数学を学ぶ上でも、そしてさらに数学や科学、その他の学問の探究の道、そして、様々な仕事をこなす上でも、諸々の難題にぶつかったときにどのように答えを導き出し、解決していけばよいのかということの大きな手段を得られたのではないかと思います。それでは、実際にこのような考える方法をこの高校数学マスターの高校数学の範囲で活用して身に付け、考える力を自分の実力へとつなげていきましょう。
論理をより深く学びたい方へ
論理のあり様
論理についてさらに深く学びたいという方のために説明しておくと、論理という言葉で語られる学問は時代や分野と共に常に革新を続けて発展してきました。様々な学問と相互に関係し合いながら、そして、時に大学者が現れて新たな知見が提唱されるということを繰り返してきたと言えます。そのため、各学問分野によって異なる様相を呈していたり、特殊化されていたりすることもあります。したがって、合理的に物事を考える方法を読んで頂けた方は、この点をより深く理解して頂けると思いますが、このページで行った論理の解説もその一つの捉え方に過ぎないということになります。
冒頭で述べた通り、論理とは、その目的は合理的に考え述べること、にあります。つまり、真理を探究するために物事や自らの考えを整理し分析し論述するための普遍的な法則が論理ということになります。しかしながら、ソクラテスが無知の知で主張するように、完全に普遍的な論理法則の発見はされていないようですし、多くの学者がこれまでもこれからも、できる限り一般的で個別的にも正確な論理法則の発見を求め続けていく、というのが実際のところだと思います。
数学のように物事の物質的な真理を探究する学問に通じる論理については、数理論理学の発展により一つの成功を収めたように見えます。しかし一方で、ソクラテスが強く興味を持つような「物事の物質的ではない側面」においては、論理はほとんど役に立たないと感じます。したがって、物事の物質的ではない側面の影響が強い学問ほど、論理という枠組み自体が多くの矛盾を抱えがちになると感じます。
数理論理学との違い
そこで、高校数学マスターでは上述してきたように、論理を「物質的な真理を探究するために物事や自らの考えを整理し分析し論述するための普遍的な法則」として一般的に捉え、そのための必要条件として、対象、関係、分解、列挙などに着目するという構成を取っています。
しかしながら、とりわけ数理論理学においては、このような構成は取っていません。数理論理学においては、前述の「推論規則について」の説明のように、数学の骨格である推論関係の厳密性に論点を集中させています。したがって、数理論理学において、論理と言えば主に推論についての議論であると考えて良いと思います。
異なる構成の理由
では、なぜ高校数学マスターでは、高校数学を学ぶための教材なのに数理論理学の枠組みで論理を語らないのかという疑問が生じると思います。それは、高校数学マスターの目標が、高校数学を学ぶことと共に、高校数学を通して考える力を身に付けることにもあるからです。そのため、数学のみならず他分野にも通じる「物事を合理的に考える方法」を学ぶためには、数理論理学の枠組みに固執しない方が良いだろうと判断しました。
デカルトは、それまでの論理学を煩雑で論述の用には足りるが、真理探究、つまり考察の用には足りないとして、簡素な思考手順を代わりとしました。数理論理学における推論や集合などの論理的に厳密な構成は、数学の研究や思考を下支えする強力な道具となっています。しかしながら他分野において、集合やそれに伴う写像などの対象や関係を整理するための道具を適用することや、形式的な推論の理論を構築して適用することは、なかなか容易なことではありませんし、上手く機能しない場合もままあります。
そのため、高校数学マスターでは、できる限り応用範囲が広く、さらに考察の用にも足りる論理的な枠組みとして、対象、関係、分解、列挙などに着目するという構成を取りました。それは、前述の命題、集合、推論の説明によっても分かって頂けると思いますが、主に「対象と関係」によって物事や自らの考えを整理して分析する方法は、枠組みとして十分に本質的かつ抽象的で、それら命題、集合、推論などを包含し、下支えすることのできる枠組みでもあるからです。くわえて、何よりも簡素で、応用範囲も広く、実際の様々な考察においても用足りると感じるからです。それは、数学においても同様の効果があると感じています。
思うに、正しさを求めるのであれば、疑問を持って根拠を求め、推論という形式を採用せざるを得ないのが学問における人間の思考であって、ソクラテスはその推論の限界をも指摘しつつ、デカルトもその限界を意識しながら推論の可能性を突き詰めて行ったのではないかと思います。推論という形式を意識しながら、ソクラテスもデカルトも推論という形式に未だ落とし込むことができていない真理をいかに探究すれば良いのかということを模索していたように思います。物事を対象と関係に分けるという枠組みは、それ自体もやはり一つの形式ですが、そしてやはり推論という形式を意識することが必須ではありますが、推論以前の物事に対する人間の認識や理解を整理する枠組みとして、それなりに有効なのではないかと思います。
実際に、科学論文であればいざ知らず、一般の小論文を推論という形式にがちがちに落とし込むことをせず、そしてそれができないのは、正しいとは一概に言えないもやもやとした情報の整理が、人間が正しいと認識できるための前段階にあり、そして推論という形式の下支えになっており、ほとんどの人間の思考が、つまり一般の小論文が、推論という形式に落とし込むに至らない知識であるからだと思います。それは、人間には明らかにそして絶対的に経験も思考力も足りない分野が、この世界のほとんどを占めているからです。
ソクラテスも推論という形式を用いて論敵を論破しながら、一方でそれを無知の知の証明としました。デカルトも推論という形式を主軸に置きながら、その前提には知識の分解を思考の規範としました。どちらも推論のみでの考察についてその限界を意識しているわけです。物事を対象と関係に分けるという枠組みは、そのもやもやとした情報の整理や、ソクラテスが捉えられないとし、デカルトが分解によって捉えようとした真理を考察するにあたり、推論と同様に明らかに不完全ながらも、ほんの少しの助力を与えてくれるのではないかと感じています。
より詳しく知りたい方は、前述の公理や原理の具体例の余談部分や、私のHPの対象と関係についての説明などをお読みください。論理について~デカルトに基礎を置いて~という論理と方法序説を解説した記事も連載中です。よろしければご参照ください。
主に推論を主軸においた、考察の用に足りる論理の実践例としては直線と平面のなす角、その最小値性 ~論理と直観の解説と共に~もご参照ください。
高校数学マスターの価値
高校数学マスターの目標に照らして考えれば、おそらく多くの方に、論理とは何かと題して、数理論理学を前面に出して主に推論、そして命題、集合などについての議論を、高校生等に向けて細々と正確に紹介することよりも、このような構成を取る価値を理解して頂けるのではないかと思います。
数学は、論理的に考察するために推論だけではなく、集合や写像などの様々な道具を発見し、厳密化をし続けてきました。数学を学ぶためにはそのような数学の概念をきちんと理解することが大切です。高校数学マスターでは、そのような数学の道具以前、背景にある考察方法を説明していると考えていただいて良いと思います。
多くの数学の苦手な方は、深くか浅くかの別はあるとしても、その数学以前、背景にある考え方を学ぶ機会が十分になかったために、数学の理解が進まないのだと感じます。したがって、数学の苦手な方には、高校数学マスターで説明するような数学の道具以前、背景にある知識こそが、苦手克服のための強力な武器になると思います。同時に、数学が得意な方にとっても、数学を深く考え、探究を行うための強力な武器になるはずです。
真理探究の枠組み
そもそも真理の探究は、真理が分からないから行うのであって、何らかの考える枠組みを前提として良いかも本来は分からないはずです。しかも、ソクラテスの言うように完全な枠組みを人が理解することはできないでしょう。そうであるならば、考察のために用いられる枠組みには、おのずと適切な適用範囲、正確性や効果の限界が生じるのだと思います。すでに知られている枠組みでは、その適用範囲、正確性や効果を超える真理を発見することはできないからこそ、さらに優れた枠組みを常に求め続ける必要性があるのだと思います。
くわえて、適用範囲を狭めれば狭めるほど具体的な枠組みの発見は容易になり、その枠組みを用いた考察の正確性や効果は高まりますが、こぼれ落ちる真理も増えていくのだと思います。このような視点からすると、適用範囲をできる限り大きく取ろうとするのが論理であって、適用範囲を狭めてでも正確性や効果を最大化しょうとするのが科学なのかもしれません。数学は、その間にあるのだろうと思います。
真理探究における価値
したがって、数学でも他分野であっても考察の一歩目は、できる限り普遍的で抽象的で簡潔な枠組みを用いることが、多くの真理をつかみ取るために必要なことだと思います。そのため、主に「対象と関係」を用いるこのページで説明した考察方法は、数理論理学で学ぶ推論や集合などの知識よりも、学問や勉強、つまり、真理の探究において度々表れる考察の一歩目の用に足りるのではないかと思います。
思えば、学問や勉強を理解を持って進めることは、考察の一歩目の連続とも言えます。そのために、広い適用範囲を持つ合理的に物事を考える方法や論理を身に付けることは、学問や勉強の理解を深め、進度を早めるための強力な武器になるのだと思います。
論理をより深く学ぶために
もし、より深く論理を学びたいのであれば、大体、関係の深い学問分野といえるのは、哲学、数学、言語学、法律学、社会学、宗教学などでしょうか。単に論理学という学問分野は、哲学の中に含まれるかと思います。数学の中の論理学は、すでに何度も言及してしまいましたが、数理論理学、数学基礎論などと呼ばれる分野に含まれます。特に、数理論理学は、19世紀においてその内容が形成された若い学問で、現代の数学を支える理論的な基礎になっていますので、大数学者を目指すのであれば早い段階で学ぶべき分野の一つと言えます。
というのは、ギリシャ数学や現代数学の発展を見ても、論理的な基礎の革新がその後の数学の発展を促すという歴史がどうも見て取れるからです。さらに余談ですが、19世紀の数理論理学の形成のきっかけは集合の発見によるところが大きかったのですが、現代の数学においては圏論という分野も数理論理学の発展を刺激する存在になりつつあるとも言われています。ぜひ大学にて勉強してみてください。
参考文献:
「たのしいすうがく2 不完全性定理 数学体系のあゆみ」野崎昭弘,日本評論社,1996年9月20日
(2021/7/28日現在、日本評論社では在庫不足でオンラインでは手に入らないそうです。ちくま学芸文庫から同タイトル同著者の文庫が出ているようです。不完全性定理 – 数学的体系のあゆみ Math&Science)
「論理がはじめてわかる 新・論理考究」本橋信義,幻冬舎メディアコンサルティング,2016年9月27日
「数学セミナー増刊 数学ガイダンス2018」数学セミナー編集部 編,日本評論社,2018年3月10日
著者:L&M個別オンライン教室 瀬端隼也
公開日:2019年1月30日
修正日:2020年1月23日 「4-3.異なる構成の理由」に、四段落「思うに、正しさを求めるのであれば、~」「実際に、科学論文であればいざ知らず、~」「ソクラテスも推論という形式~」「主に推論を主軸においた、~」を追加しました。
修正日:2021年2月24日 参考文献に「たのしいすうがく2 不完全性定理 数学体系のあゆみ」と「数学セミナー増刊 数学ガイダンス2018」を追加しました。


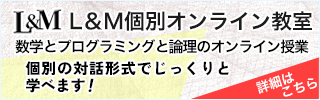
※このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。そのためGoogleのPrivacy PolicyとTerms of Serviceが適用されます。