東京大学・令和4年第2次前期・数学(理科)第二問の解説と解答
【目次】
0.はじめに
1.解説と解答
1-1.小問(1)
1-2.小問(2)
1-3.小問(3)
2.まとめ
はじめに
今回は、過去問の第二回として「東京大学・令和4年(2022年度)第2次前期・数学(理科)第二問」の解説と解答を示します。できるだけ計算や論理に飛躍のないように、くわえて解説も含みますので解答としてはもっと簡潔に記載するようにしてください。誤記・誤答につきましてはご指摘を頂けますと幸いです。
東京大学の著作権保護のため問題文は下記のページよりご確認ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_04_22.html
解説と解答
それでは、前回一般的な受験対策と東京大学・令和4年第2次前期・数学(理科)第一問の解説と解答で解説しました通り、「教科書に書かれた基本を思い出して問題文の指示に素直に従うこと」を大切にして一つ一つ小問を解いていきましょう。
小問(1)
まず、問題文から数列の漸化式の問題だと分かります。高校数学の教科書(詳しくは、高校数学マスター基本方針:参考にする教科書を参照ください。以下同じ。)の数学B第3章「数列」第2節「数学的帰納法」7.「漸化式と数列」の内容を思い出しましょう。
そして、小問(1)を読むと、正の整数、つまり自然数における\(a_n\)の性質(5の倍数か?)を問題としていると分かるので、数学B第3章「数列」第2節「数学的帰納法」8.「数学的帰納法」B「数学的帰納法による整数の性質の証明」や数学A第3章「整数の性質」第1節「約数と倍数」が思い浮かぶと思います。さらに、小問(1)(2)をざっと見ておくと、つながりはよく分からないなと思いながら、まずは一つ一つ小問(1)から解いて行こうと解答を始めると思います。
そこで、数学Bの「数学的帰納法による整数の性質の証明」で解こうと思い浮かぶ方がいるかと思いますが、数学的帰納法を素早く使える方であれば良いと思いますが、一般的には考えを整理するのに時間がかかるので、数学A第3章「整数の性質」第1節「約数と倍数」3.「整数の割り算と商および余り」の特に研究「割り算の余りの性質」さらに発展「合同式」を使おうと方針を定めます。
というのは、この二つを理解しておけば数列が5の倍数であるかという整数の性質については、数列を具体的に計算しなくとも余りだけを計算すれば良いということが分かっているからです。簡単に説明すると、\(a_n\)を5の商\(q\)と余り\(r\)で\(5q+r\)と表したときに、それらの足算・引き算・掛け算の結果で、5を必ずしも含まない項は余りの足算・引き算・掛け算だけになり、他の項は必ず5を含みそのため5で割り切れるからです。この点について忘れている方は、もう一度、教科書の該当箇所を復習してみてください。
そうすると、\(a_n\)を5で割った余りの数列は、先頭から\(1,2,0,1\dots\)と続き、漸化式の結果は前項の結果のみで決定するので、\(n=4\)にて先頭の\(a_1=1\)に等しくなり以降はこの繰り返しになると分かります。したがって、\(n\)が3の倍数のときは、\(a_n\)が5の倍数となることが分かりました。
□
念のため解答例を示すと、「\(a_n\)を5で割った余りの数列は、先頭から\(1,2,0,1\dots\)と続き、漸化式の結果は前項の結果のみで決定するので、\(n=4\)にて先頭の\(a_1=1\)に等しくなり以降はこの繰り返しになる。」あるいは「\(a_n\)を5で割った余りの数列は、先頭から\(1,2,0,1\dots\)と続き\(n=4\)にて先頭の\(a_1=1\)に等しくなり以降はこの繰り返しになる。」となります。後述する小問(2)小問(3)も解説のため長くなっていますが、解答例としては短く簡潔になりますので、お時間があれば抜粋して簡潔に解答例を示す練習をしてみてください。
小問(1)は、教科書に書かれた基本を思い出せば「数学的帰納法による整数の性質の証明」でも「割り算の余りの性質」や「合同式」でも解ける内容だと思います。問題集を解きなれている必要はあると思います。
出題の背景を少し説明すると、「整数の性質」という分野は、出題をする数学者の先生方にとって「数学者」というだけあって大変強い興味を持った方の多い分野です。また、応用も近年増え続けておりますし良問ができたら出題したくなる分野と言えるかもしれません。その基礎的な「初等整数論」という分野は高校生でも手を付けやすくかつ奥深い内容を含んでおり、この分野に多少なりとも親しむと上記の考え方は基本的な考え方になっていきます。
小問(2)
さて、小問(2)は小問(1)と何か関係するかな、と思って読んでみてもあまりに一般的な法則なので使えそうにないなという結論におそらくなります。特に試験中に小問(1)から他の例を類推して確かめてさらに抽象して小問(2)に答えられる方はかなり稀だろうと思います。
そこで、「\(a_n\)が\(a_k\)の倍数である」ということは、\(a_n \equiv 0 \pmod {a_k}\)なので、まず、漸化式を使って\(a_n\)を\(a_k\)で表せないかと考えます。そうすれば、\(a_n \equiv 0 \pmod {a_k}\)と同値な\(a_k\)を含んだ合同式(の方程式)を作れますし、\(\pmod {a_k}\)を取ることで\(a_k \equiv 0\)になるのでその合同式(の方程式)を簡単にできるだろうと想定します。そうすれば何か条件が見えてくるかもしれません。
この時点で、数学A第3章「整数の性質」第1節「約数と倍数」3.「整数の割り算と商および余り」発展「合同式」をかなり使いこなせていないと時間内に解き切るのは難しい、つまり、普通の高校生にとっては「教科書に書かれた基本を思い出して問題文の指示に素直に従うこと」では解けない、「解けなければ何か問題に隠されたアイデアを求めて試行錯誤をしてみる」ことが必要な難問に入るかもしれないと思います。ただ、「初等整数論」に親しむ数学好きの高校生にとっては難しくはない問題かもしれません。
漸化式を使って\(a_n\)を\(a_k\)で表すと次のようになります。
\[a_n = (\cdots(a_k^2+1)^2+1)^2 \cdots + 1)^2 + 1\]
そして、後ろに続く\(+1\)の個数は、漸化式を適用した回数、つまり、\(n-k\)個であると気付きます。そこで、\(\pmod {a_k}\)を取れば\(a_k \equiv 0\)になるので、
\[a_n \equiv (\cdots(0^2+1)^2+1)^2 \cdots + 1)^2 + 1 \pmod {a_k}\]
さらに、\(a_1 = 1\)であることに気付けば、
\[a_n \equiv (\cdots(a_1)^2+1)^2 \cdots + 1)^2 + 1 \pmod {a_k}\]
となり、\(+1\)の個数は一つ減って\(n-k-1\)個になります。そうすると上記の右辺は漸化式を適用すると、
\[a_n \equiv a_{n-k} \pmod {a_k}\]
となります。これは、「整数の性質」で割り算と余りについての理解を深めておけば、割り算が引き算の繰り返しであるということを理解できているはずなのでこの式を繰り返し適用して、\(n\)を\(k\)で割った余りを\(r\)とすると、
\[a_n \equiv a_r \pmod {a_k}\]
であることが分かります。さて、そうするとこの式の意味は、小問(1)で行ったように\(a_n\)を\(a_k\)で割った余りの数列\(r_n\)を考えると、\(n\)番目の項\(r_n\)は\(n\)を\(k\)で割った余り\(r\)番目の項に表れる\(a_r\)に等しくなる、\(r_n=a_r\)ということだと分かります。\(r\)は\(k\)で割った余りですので\(0\)から\(k-1\)しかありません。つまり、余りの数列\(r_n\)は先頭から\(a_1, a_2, a_3, \cdots a_{k-1}, a_{k}\)と続いて、あとはその繰り返しになるということが分かります。
ここで、\(a_1, a_2, a_3, \cdots a_{k-1}, a_{k}\)はこの漸化式は単調増加しますので、その中の\(a_1, a_2, a_3, \cdots a_{k-1}\)は\(a_{k}\)では割り切れません(\(\not \equiv 0 \pmod {a_k}\))。一方で、\(a_{k}\)は\(a_{k}\)で割り切れます(\(\equiv 0 \pmod {a_k}\))。これが延々とどこまでも繰り返しますので、つまり、\(n\)が\(k\)の倍数の場合は\(a_{k}\)で割り切れ、それ以外は\(a_{k}\)で割り切れないことが分かりました。
したがって、\(a_{n}\)が\(a_{k}\)の倍数となる必要十分条件は、\(n\)が\(k\)の倍数であることと分かります。これを式で表すと、
\[a_n \equiv 0 \pmod {a_k} \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod k\]
となります。
この小問(2)は、数学的にとても興味深い内容なので作問者も楽しみながら、出題をしてみたかった内容ではないかと感じます。一方で、そうなると合同式がきちんと利用できてそれなりの論理的思考力が必要となり、短時間で一般の高校生が解くには難しい内容になっているのではないかと思います。
小問(3)
それに対して、小問(3)は\(a_{2022}\)と出題年が使われているように、おそらくこの時点で2022が数学的には特別な意味を持つ数字ではないだろうという予想が付き、というように小問(2)とは趣が異なります。
どのような点が異なるかというと、一般的に数学の問題、特に難問というのはそれを知りたいという人や数学史的な動機はあってもその解決や解答に人の意図の入る余地はありません。ただどう自然が成立しているのかということを読み解くことになります。一方で、時間制限があって知識の習得等を確認するための受験問題は、作問者の意図が強く反映されますので、作問者は何を聞きたいのか、あれかな、これかな、という読解力を問われているところがあり、作問者の意図の流れを素直にたどっていく方が正答率があがるはずです。
この意味で、小問(2)は数学的な面白さのある前者の問題に近く、小問(3)は遊びの要素のある後者の問題と言えるかと思います。実際に、小問(2)を解く能力がある人は小問(3)を解ける可能性が高く、小問(3)は小問(1)と小問(2)を使えばそれほど難しくなく解ける問題です。小問(2)を解いた人へのボーナス問題のような位置付けにも見えます。
さて、小問(3)は、\(a_{2022}\)と\((a_{8091})^2\)の最大公約数を求めよということですが、二つの数の最大公約数を求めるといえば数学A第3章「整数の性質」第2節「ユークリッドの互除法」4.「ユークリッドの互除法」ですが、計算のために必要な各数は具体的には分かりそうもありません。そう思って数列の項の数をみると2022と8091で、
\[8091=2022\cdot 4 + 3\]
と2つの数が関係ない数というよりは、余りが3で少ない数という強い関係のある数であることに気付きます。そこで小問(2)を使うと、\(2022\cdot 4=8088\)は\(2022\)の倍数なのだから\(a_{8088}\)は\(a_{2022}\)の倍数だと気付き、これを使うのではないだろうかと考えてみます。ここら辺が読解力?なのかもしれません。
そこで、上記の項数の余りが3ということは、漸化式であれば\(a_{8088}\)から3回適用すれば\(a_{8091}\)になるということに気付けば、小問(2)で考えたような合同式を\(a_{2022}\)を法として考えてみようという気になります。そうすると、
\[(a_{8091})^2 \equiv (((a_{8088}^2+1)^2+1)^2+1)^2 \equiv ((1^2+1)^2+1)^2 \equiv 25 \pmod {a_{2022}}\]
となることが分かります。そして、数学A第3章「整数の性質」第1節「約数と倍数」3.「整数の割り算と商および余り」発展「合同式」を理解しているだけでは少し難しいかもしれませんが、合同式をきちんと理解していれば上記の式から
\[(a_{8091})^2 = l\cdot a_{2022} + 25\]
という商と余りの式が書けて、数学A第3章「整数の性質」第2節「ユークリッドの互除法」4.「ユークリッドの互除法」をきちんと理解していれば解けそうなところまで来ます。つまり、ユークリッドの互除法は、割られる数と割る数の最大公約数と割る数と余りの最大公約数が一致するという法則を使って二つの数の最大公約数を求める計算法でした。この点を忘れている方は教科書(p.130)を見直してください。
したがって、\((a_{8091})^2\)と\(a_{2022}\)の最大公約数を求めるには、\(a_{2022}\)と\(25\)の最大公約数を求めれば良いことが分かります。そして、\(25\)の約数は\(25,5,1\)しかありませんので、このいずれかが最大公約数になるところまで絞れました。そこで、5の倍数というところで小問(1)を思い出し、\(2022\)が\(3\)で割れれば\(a_{2022}\)は5の倍数になりますが、たしかに\(2022=674\cdot 3\)と割り切れるので\(a_{2022}\)は5の倍数であることが分かります。
そうすると、最大公約数の候補\(25,5,1\)のうち\(1\)ではないことが分かりましたので、\(25,5\)のいずれだろうかという話になります。そこでやはり、5の倍数であることを確定した小問(1)のやり方を思い出し、今度は25の倍数ではないかを同様のやり方で確かめられないかと考えてみます。つまり、小問(1)では、5の余りだけに着目して数列を計算してみたので、今度は25の余りだけに着目して数列を計算してみます。
そうすると、余りだけの計算で良かったので計算は簡単で、\(a_n\)を25で割った余りの数列は、先頭から\(1,2,5,1\dots\)と続き、漸化式の結果は前項の結果のみで決定するので、\(n=4\)にて先頭の\(a_1=1\)に等しくなり以降はこの繰り返しになると分かります。そして、どの項\(n\)でも25で割った余りが\(0\)にならないということは、25で割り切れないということなので、\(a_{2022}\)も25では割り切れないことが分かりました。
したがって、\(a_{2022}\)と\(25\)の最大公約数は\(5\)であることが分かり、つまり、\((a_{8091})^2\)と\(a_{2022}\)の最大公約数も\(5\)であることが分かりました。
まとめ
小問(3)のような論理的に約数や素因数や余りを絞る問題は教科書でも解説され、問題集でも多く問題を見ることができると思います。ただ、小問(3)はきちんと教科書の内容を理解した上で合同式まで理解をしていないと解きにくいかと思いますので難易度としては高めの問題かと思います。
数学への関心の持ち方は多様なものでその方が良いと思いますが、一つの典型的な数学への入り口として数に関心を持ち中学・高校のうちから歴史的な偉人、例えばフェルマー、オイラー、ガウスなどと探求していくうちに自然と初等整数論に興味を持つことが想定されます。この問題は、そのような将来有望な典型的な数学好きの高校生たちへのボーナス問題かなと感じます。初等整数論では、この問題のように約数や素因数や余りを絞る論理的な操作が基本の一つとなり、様々な数に親しむことでたくさんの発見と驚きを味わうことができます。
最後に各小問について振り返ると、小問(1)は教科書の基本に沿って解くことのできる問題で教科書で紹介されている合同式を使えるようになっていると簡単に解くことができます。小問(2)は合同式を使いこなせていないと解くのが難しい問題ではないかと思います。時間内に解き切るには論理的な思考力も必要になると思いますし、初等整数論をある程度学んだことのある方には有利な問題です。小問(3)は、やはり初等整数論を学んだことのある方には有利な問題で、ただし小問(2)とは違って作問者の意図を読みながら小問(1)と小問(2)を上手く使う必要がある受験問題らしい問題と言えるかと思います。
著者:L&M個別オンライン教室 瀬端隼也
公開日:2023年5月5日
修正日:-


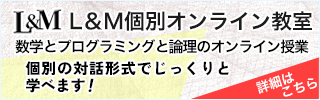
※このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。そのためGoogleのPrivacy PolicyとTerms of Serviceが適用されます。